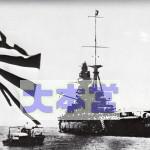金剛級画像集
画像をクリックすると大きくなります。
追加予定あります
- 昭和12 年大改装が完了した金剛
- 大正4年の比叡 ほぼ完成時の姿です 佐世保にて
- 第一次改装後 画像は霧島
- 榛名大正3年 川崎造船所にて艤装中
- 霧島へ砲塔旋回部取りつけ
- T2 比叡 横須賀
- 昭和8年、練習戦艦になった比叡。 4番砲塔がありません
- 大正10年 佐世保に入渠して整備中の霧島
- 昭和8年横浜沖大観観式お召し艦比叡が艦列をぬって行く
- 御大礼特別大観艦式のお召艦榛名
- 東京湾をゆく比叡の雄姿 昭和17 年
- 昭和8年横浜沖大観観式 比叡の後楼トップに天皇旗が翻る
- 明治45年建造中の霧島の艦尾方向を見る 艦底2重底を張りつけ中
- 大正2年日本への廻航を待つ金剛 遠方は建造された船渠で、母と別れを惜しんでいるように見える
- 大正4年撮影の霧島
- 昭和14年霧島と赤城
- 昭和12 年、大改装が完了し高速戦艦となった金剛
- 昭和3年、大改装完了の榛名を見学した尋常小六年、高等小1,2年生の記念写真
- 進水式前の霧島の艦尾 スタン・ウォークが良く判ります
- 昭和20年、呉で大破着底した榛名
金剛級の戦艦は当初「巡洋戦艦」として計画されたものです。
ネームシップ金剛が1911年に英国ヴィッカース社で建造開始されました。
日露戦争後、帝國海軍は薩摩級を進水させて主力艦の国産化に目処をつけることができました。ところが英国が高速かつ強武装の革命的戦艦「ドレッドノート」を就役させると、艦隊に入る前から旧式艦と化してしまったのです。
ドレッドノートは新形式のタービン駆動を導入して高性能を実現していたのです。
戦艦「安芸」、巡洋戦艦「伊吹」に輸入モノのタービンを搭載してみたものの、どうもいま一つパッとしません。そこで、今一度師匠の教えを請うてみようと言うワケでした。
2番艦比叡は横須賀海軍工廠で、3番艦榛名は神戸川崎造船所、4番艦霧島は三菱長崎造船所で建造されました。日本の民間造船所で主力艦が建造されるのは初めてのことでした。
金剛級の変遷
| 竣工時 | 第一次改装 | 第二次改装 | |
| 排水量 | 26,330トン | 29,300 トン | 32,000トン |
| 全長 | 214.6m | 214.6m | 222m |
| 全幅 | 28.04m | 28.04m | 31.02m |
| 主機 | 2基4軸 64,000馬力 | 2基4軸 64,000馬力 | 4基4軸 136,000馬力 |
| 最高速 | 27.5ノット | 25ノット | 30ノット |
| 兵装 | 35.6cm45口径連装砲4基 | +水偵3機など |
ネームシップ金剛は帝國海軍が外国に造らせた最後の主力艦となりました。
海軍工廠ばかりでなく、神戸川崎造船所、三菱長崎造船所からも大勢の技師・職工らがヴィッカース社へ研修に訪れて技術輸入に努め、我が国の造船術は大きく進歩しました。
残念なのは金剛級のゆとりを持った設計の極意と言うか、精神・思想を受け継ぐことが出来なかった点です。
これは金剛級の3番・4番主砲塔の配置に良く現れています。
もう一基砲塔を置けそうなんですが、あえて開けているんです。これが出来なかったのが、独自設計した次級の扶桑級で、結果は高速戦艦に変身できるか否かに出てしまいました。
金剛級には逐次改装が行われましたが、大きなものは2回。
第一次改装はユトランド海戦の結果を受けて装甲を強化したものです。
このために排水量が3000トンほど増加し、速力も落ちたために艦種を巡洋戦艦から戦艦に変更されました。
続いて速力向上のために主機(タービン)、罐の交換、艦体の延長などを行い、高速戦艦となって大東亜戦争に突入しました。
大東亜戦争で、最も古く、最も活躍した戦艦級となりました。
個艦別の活躍はこちら
「金剛」
「比叡」
「榛名」
「霧島」